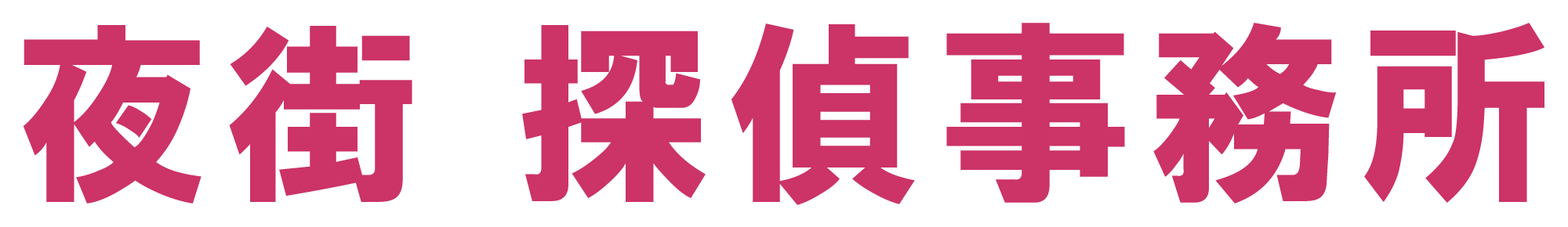企業にとって従業員による金銭トラブル、特に横領や着服といった不正行為は深刻な経営リスクとなります。多くの事例では、信頼関係を背景に発覚が遅れ、被害額が拡大してから問題化する傾向にあります。これを未然に防ぐためには、定期的な会計監査を行い、不正の兆候を早期に察知する体制を構築することが必要です。また、内部告発制度やホットラインなど、従業員が声を上げやすい仕組みの整備も重要な予防策のひとつです。本記事では、企業が取り組むべき金銭トラブル予防の具体策や、再発防止の体制構築について詳しく解説します。
- 会計担当者に業務が一任されている
- 現金管理や仕入れ精算が属人的である
- 過去に小規模な金銭ミスが見られた
- 社内に内部告発制度が整備されていない
- 不正防止に関する研修や教育が実施されていない
見えにくい内部リスク、金銭トラブルはなぜ起こるのか
企業内で起こる金銭トラブルの実態
近年、企業における従業員による金銭トラブル、特に横領や着服といった不正行為の発覚事例が増加しています。特に中小企業では、経理や現金管理を一部の信頼された社員に任せきりにしていることが多く、長期間にわたる不正が見逃されてしまう傾向があります。被害額が数百万円から数千万円に及ぶケースも珍しくなく、経営を揺るがす深刻な問題に発展することもあります。こうした問題は、業務の属人化、監査体制の不備、職場の緊張関係など、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。企業は「うちには関係ない」と思わず、常にリスクを意識する必要があります。
発覚の遅れがもたらす経営リスク
従業員の不正行為は、発覚が遅れれば遅れるほど被害額が大きくなり、企業の信用や存続にまで影響を及ぼします。長年勤めていた社員による不正ほど、発見までに時間がかかる傾向があり、内部告発や偶然の発見をきっかけに明るみに出るケースが多いです。さらに、金銭トラブルが外部に報道されると、取引先や顧客からの信頼を失い、経営の継続が困難になることもあります。従業員による犯罪行為は、警察対応や損害賠償請求といった法的措置に発展するため、経営者にとって重大な危機管理課題といえます。
発覚の遅れによる影響
- 被害額の増大|長期間にわたる不正で損失が膨らむ
- 企業の信用低下|不正が報道されると取引先や顧客の信頼を喪失
- 法的対応の負担|警察対応や損害賠償請求で企業側の負担が増す
- 社内の混乱発生|職場内の人間関係や業務体制に大きな影響
- 経営継続の危機|資金繰りの悪化や倒産リスクに発展する可能性
不正行為が発生しやすい職場の特徴
金銭トラブルが発生しやすい職場にはいくつかの共通点があります。たとえば、現金や領収書の取り扱いに関するルールが曖昧であること、業務が一部の担当者に集中していること、そして日常的なチェック体制が不十分であることです。また、従業員が精神的・経済的に追い詰められている場合や、職場内に相談できる環境がない場合も、不正に手を染めやすくなる要因となります。組織内での信頼関係が極端に偏っている場合、「この人なら大丈夫」という思い込みがチェックの甘さに繋がることもあり、トラブルの温床となりやすいのです。
内部不正の可視化と責任追及のために
金銭トラブルに対する証拠収集の基本
従業員による金銭トラブルを企業が正当に対応するためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。「おかしい」と感じた段階で口頭の注意や内部処理で済ませるのではなく、不正の疑いがある行為について正確に記録を残すことが重要です。たとえば、不自然な出金や伝票の改ざん、業務外の口座振込、私的流用が疑われる領収書などを、時系列に沿って整理・保管しておく必要があります。また、会話の録音や防犯カメラの映像も有力な証拠となります。企業として法的措置や懲戒処分を行う際、確実な証拠がなければ逆にトラブルの火種となりかねません。
証拠として有効な資料と記録の種類
企業が従業員の不正を立証するために必要な証拠は多岐にわたります。たとえば、帳簿と実際の金額が一致しない記録、虚偽の報告書、金銭の流れが不明瞭な経費精算書、関係者とのメールやチャットの履歴などが該当します。これらは、社内調査において本人への確認や弁明の機会を与える際にも重要な資料となります。また、通帳の写しや取引履歴、ICカードの入退室記録など、物理的な動きや金銭の流れを裏付ける記録があれば、不正の立証がより確実になります。記録の保存は改ざん防止の観点から、第三者によるチェック体制下での管理が理想です。
有効な証拠の例
- 帳簿と現金の不一致|記録と実際の金額に差異がある会計データ
- 虚偽の報告書|事実と異なる内容が記載された業務資料
- 不明瞭な経費精算|使途不明な領収書や現金使用履歴の記録
- 不正を示すやり取り|関係者とのメール・チャット・メッセージ履歴
- 入退室や取引履歴|ICカードの記録や銀行の入出金履歴など
証拠の扱いで注意すべきポイント
不正の証拠を集める際には、法的トラブルを避けるためにも慎重な対応が求められます。たとえば、本人に無断で私物や個人メールを調べたり、過度に監視を行うことはプライバシー侵害となる恐れがあり、逆に企業側が訴えられる可能性もあります。証拠の収集は、業務上の正当な権限の範囲内で行う必要があります。また、本人への事情聴取や事実確認の場を設ける場合は、必ず複数人で対応し、記録を残すことが重要です。証拠は「集めること」だけでなく、「正しく保管・運用すること」がトラブルの再発を防ぐ鍵となります。
社内でできる予防と対応
社内で実施できる初期対応と記録整理
従業員の金銭不正が疑われた場合、企業としてまずできることは、冷静な記録整理と事実確認です。関係する帳簿や経費精算書、伝票の控えなどを集め、時系列で整理することが基本です。また、日々の金銭管理に関わる業務内容を見直し、誰が何をどのように扱っていたかを明確にすることで、誤解や漏れを防ぐとともに、不正の可能性を把握しやすくなります。社内での聞き取り調査を行う場合には、複数名で実施し、必ず記録を取りながら慎重に進めることが重要です。初動対応を適切に行うことで、後のトラブル拡大を防げます。
自社対応の利点とその限界
社内で早期に対応することのメリットは、外部への情報漏洩を防ぎながら、柔軟に対応できる点にあります。特に、確認段階で事実関係がはっきりしない場合は、社内の調整で円満に解決できる可能性もあります。しかし一方で、不正が複雑化していたり、金額が大きい場合は、自社だけでの対応に限界があります。曖昧な調査や対応が、後に従業員からの逆告発や労務トラブルに発展することもあります。初期対応の段階で少しでも不安がある場合には、外部の専門家に相談し、証拠の取り扱いや対応方針についてアドバイスを得ることが望ましいでしょう。
再発防止のための内部体制の見直し
金銭トラブルの発生を未然に防ぐためには、制度や業務体制そのものの見直しが欠かせません。たとえば、金銭の取り扱いや精算に関わる業務を一人に集中させず、複数人でチェックする仕組みを導入することが有効です。また、内部監査の定期実施や、匿名で通報できる内部通報制度(ホットライン)の整備も、従業員に不正を「させない・隠させない」環境づくりにつながります。さらに、社内教育として倫理研修や事例共有を行うことで、金銭管理に対する意識を高めることも重要です。防止体制の構築こそが、企業の信頼を守る土台となります。
不正の解明と再発防止へ
専門家による証拠収集
従業員による金銭不正が疑われる場面では、企業が自力で収集できる証拠に限界がある場合も多く、探偵や会計士、弁護士といった外部の専門家に依頼することで、より正確で客観的な証拠収集が可能となります。例えば、業務用パソコンや社内ネットワークの操作履歴、改ざんの痕跡、複数の帳簿の突合など、専門的知識と技術を要する調査も対象になります。また、外部機関の関与により、社内調査に対する公平性と信頼性が高まり、従業員や関係者からの納得も得やすくなります。初期の段階で専門家が関与することで、後のトラブルも未然に防ぎやすくなります。
専門家によるアフターフォロー
証拠収集や不正の発覚後には、調査だけで終わらせず、事後対応まで見据えた支援が求められます。専門家に依頼することで、懲戒処分や退職勧奨の手続き、被害金の回収交渉、法的手段の検討など、状況に応じたアドバイスや実務サポートを受けることができます。また、再発防止のための社内制度の見直しや監査体制の構築支援、社内向けの研修企画など、広範な分野でのフォローアップも可能です。不正対応は一度きりの処理ではなく、組織としての「信頼回復」や「体質改善」にもつながる継続的な取り組みが重要であり、その道筋を専門家が導いてくれます。
専門家に依頼するメリット・デメリット
専門家へ依頼するメリットは多岐にわたります。まず、公平かつ法的根拠のある調査や対応が可能となり、社内だけでは得られない信頼性を確保できます。また、被害額の回収や適切な処分に向けた法的対応も迅速に進めることができ、企業にとってリスク管理の大きな支えとなります。一方で、費用が発生する点や、外部の関与によって社内の緊張感が高まる場合があることも留意が必要です。また、業者選びを誤ると、調査が不十分だったり、過剰な対応が逆効果となることもあります。実績と信頼性のある専門家を選び、事前に目的や対応範囲を明確にすることが成功への鍵です。
的確な依頼と納得のコスト
初回の相談で確認しておくべきこと
金銭トラブルに専門家を活用する際、最初の相談段階が非常に重要です。初回の無料相談を活用することで、自社の状況に合った対応が可能か、どこまでの調査や支援が受けられるのかを具体的に確認できます。相談時には、対象となる書類や記録、不審なやりとりの履歴などを用意し、できるだけ具体的に状況を伝えることが求められます。また、対応可能な範囲や調査の進め方、想定される日数、必要に応じてどこまでの法的支援ができるかも事前に質問しておくと、依頼後のトラブルを避けやすくなります。信頼できる専門家選びの第一歩です。
目的に合った調査・対応プランの選択
専門家への依頼は、調査内容や目的に応じて複数のプランから選択できるケースが一般的です。たとえば、簡易な経費不正の確認であれば短期間・低予算の調査で済むこともありますが、発信者の特定や法的訴訟までを視野に入れる場合は、より高度な調査や法的支援が必要となります。また、社内向けの再発防止策の提案や、通報制度構築支援を含めた包括的な対応も選べる専門機関もあります。自社が「何をゴールとするのか」を明確にし、それに合ったサポート体制を提案できる専門家を選ぶことが、無駄のない依頼につながります。
調査・対応にかかる費用の目安
従業員の金銭トラブルに対する調査費用は、内容と範囲によって異なります。一般的には、軽度な会計不正の確認や資料整理支援で3万円~10万円程度、発信者特定・弁護士の法的対応を含めると20万円~50万円以上になることもあります。また、社内制度改善や監査体制構築などの長期的サポートでは月額契約や顧問契約となる場合もあります。費用は事前の見積りで明示されるのが基本ですが、「追加料金の発生条件」「対応できる範囲」「成果が得られなかった場合の対応」なども確認し、納得のうえで契約を進めることが大切です。
探偵法人調査士会公式LINE
ナイトセーフ探偵では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。
不正発覚から再発防止までの実例紹介
経理担当の着服に気付き、証拠と対応を整備した事例
製造業を営む中堅企業F社では、経理担当者が長年にわたり経費を水増しして着服していたことが判明しました。金額は累計で約500万円にのぼり、会社内部での発見は困難な状況でした。調査専門家へ依頼した結果、過去の帳簿と伝票の突合、パソコン内の履歴調査などで不正の証拠を収集。弁護士を通じて本人と示談交渉を行い、一部返金と退職処理が円満に完了しました。現在では、業務分担と定期監査を導入し、再発防止の社内体制が整っています。
社内通報から不正判明、制度整備につながったケース
小売業を展開するG社では、匿名の社内通報により店舗責任者によるレジ現金の横領が発覚しました。通報内容をもとに調査会社に依頼し、監視カメラ映像やPOSデータをもとに裏付け調査を実施。不正が事実であることが判明し、本人に事情聴取のうえ懲戒処分が行われました。その後、企業側は内部通報制度の見直しと、従業員向けの倫理教育を強化。不正を抑止する文化づくりに成功し、従業員間の信頼も回復しています。
会計監査を通じて不正を未然に防止できた事例
IT関連企業H社では、定期的に外部の会計士による監査を導入しており、ある月次監査で交通費の不自然な申請が複数発見されました。会計士がその場で経理部にヒアリングを行い、精算内容をチェックしたところ、一部社員による水増し請求の疑いが浮上。社内で記録を精査し、専門家のアドバイスを受けながら処理を進めたことで、大きな不正に発展する前に問題を是正することができました。監査体制の有効性が証明された好例です。
よくある質問(FAQ)
不正が確定していない段階でも相談できますか?
はい、疑いの段階でも相談は可能です。むしろ、不正の可能性があると思った時点で早期に相談することが、被害の拡大や誤対応を防ぐうえで非常に重要です。初期の段階であれば、社内での対応と調査を併用して行える場合もあり、事実関係の整理や証拠の保存方法など、専門家から適切なアドバイスを受けることができます。確定してからでは手遅れになることもあるため、「念のため」の相談が企業リスクを軽減する第一歩です。情報は守秘義務のもとで取り扱われますので、安心してご利用いただけます。
調査を依頼した場合、社内の誰かに知られてしまいますか?
いいえ、調査は基本的に極秘で行われ対象者や社内の他の従業員に知られないよう慎重に対応されます。特に社内不正の調査は、発覚前に情報が漏れると証拠隠滅や問題の複雑化につながるため、専門機関は調査の機密性を非常に重視しています。また、調査結果の報告や打ち合わせも、依頼主(通常は経営者や人事・法務責任者)と限定された範囲で行われます。信頼性の高い専門家を選ぶことで、企業内の秩序を保ちながら調査を進めることができます。
不正が事実だった場合、どのような対応が必要になりますか?
不正が事実として判明した場合、企業としては懲戒処分、刑事告訴、損害賠償請求などの対応を検討する必要があります。対応の方向性は、被害の大きさや不正の内容、社内規定によって異なりますが、法的手続きに移行する前に、必ず弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。また、社内の他の従業員への説明方法や、再発防止策の発表など、組織全体の信頼維持を意識した慎重な判断が求められます。感情的な対応や独断での処理は、後に逆効果となることもあるため注意が必要です。
早期対応が企業を守る
従業員による金銭トラブルは、企業にとって他人事ではありません。どんなに信頼している社員であっても、環境や状況の変化によって不正に走るリスクは存在します。だからこそ、「起こる前提」で内部体制を整備し、日常的に不正の芽を摘み取る仕組みが必要です。定期的な会計監査や複数人によるチェック体制、内部通報制度の活用など、社内から気付ける土壌づくりが被害の予防につながります。そして、異変に気づいたときは早めに専門家へ相談し、冷静かつ適切に対応を進めることが、企業の信頼と未来を守る最大の対策になります。
※ご紹介する事例はすべて、探偵業法第十条に基づき、依頼者の安心を最優先に個人が特定されないよう配慮・修正されたものです。ナイトセーフ探偵は、夜の街で起こるトラブルに対応する専門調査サービスです。浮気やストーカー、詐欺、金銭トラブルなどに対し、迅速で確かな調査と解決サポートを提供します。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者
夜街探偵担当:北野
この記事は、夜の街で働く方やトラブル、困りごとに悩んでいる方の解決に一歩でも近づければと思い、夜街探偵の調査員として過去の経験や調査知識を生かして記事作成を行いました。困っている方たちの力になれれば幸いです。

この記事の監修者
XP法律事務所:今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。夜の街で起こるトラブルにはご自身だけでは解決が難しいケースも多く見受けられます。法的視点で解決に導くことでスムーズな解決が見込めることもあります。皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者
心理カウンセラー:大久保
夜の街で起こる問題や悩みには、誰かに相談したくてもできない問題も多いかと思います。この記事を通じて、少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで解決に進めるようにと、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中

ナイトセーフ探偵への相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
夜の街で起こる各種トラブル等の相談、探偵調査、対策サポートに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)
無料相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
トラブル対策や探偵調査の詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間利用可能で、費用見積りにも対応しております。
タグからページを探す